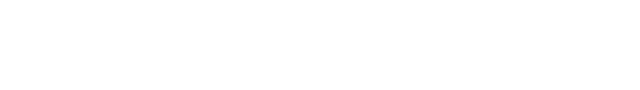減酒とお茶の習慣
当院では、アルコール性肝炎が疑われる患者様に対し、減酒の指導をさせてただくことがあります。
アルコールの影響が疑われる方では、まず、血液検査でγGTPという値が上がることが多いです。
これは、アルコールの代謝で肝臓が頑張っている証拠です。
その次の段階では、AST・ALT(GOT・GPT)という、逸脱酵素とよばれる値が上がってきます。
こうなると、いよいよ肝細胞がアルコールで障害を受けているということになります。
いわゆる、「アルコール性肝炎」の状態です。
ここからさらに多量飲酒を続けると、「アルコール性肝硬変」という状態になります。
こうなると、肝臓はもう元には戻りません。幹細胞から逸脱する酵素すらなくなって、腹水や黄疸、食道静脈瘤など致命的な合併症を引き起こします。
肝機能障害以外にも、世界保健機関(WHO)は、アルコールが頭頸部がん、食道がん、肝臓がん、大腸がん、女性の乳がんの原因となると認定しています。
古来から、「酒は百薬の長」と言われるように、適量の飲酒はむしろ健康維持に貢献すると考えられており、最近までそれが常識でした。
ところが、WHOは『The Lancet Public Health』の中でこれを否定し、アルコールに安全な量はないと言い切ってしまいました。
しかし、お酒も嗜好品と考えると、人生を豊かにする一助であるという側面は否定できません。
健康のために何でもかんでもやめろというのは無理があります。
一応、日本では現状、検診で指導する適正飲酒量というのがあり、これがアルコール量で20g, つまりビール500ml, ウイスキーならダブル1杯(60ml)です。
この3倍量を超えると健康リスクが著明上昇するとされています。
かくいう私も、1年くらい前までアルコール常飲者でした。
これはいけないと思い、いわゆる休肝日を設けようとしたのですが、酒を飲むのが当たり前の日常に休肝日を持ち込んでも、その日は「我慢」になってしまい、なかなかうまくいきませんでした。
そもそも、休肝日を守れないのはアルコール中毒の証拠ですので、これは非常にまずい状況です。
そこで発想を変えて、酒を飲まないのを当たり前にし、飲むのは翌日に仕事がない日、会食など特別な時だけとしてみました。
食後は紅茶や緑茶などのお茶を嗜むようにしたら、すんなり飲酒の習慣が無くなりました。
睡眠も深くなったせいか、朝も30分以上早く自然に気持ちよく目覚めるようになったし、日々感じていた日中のだるさや胃の不快感もなくなりました。
理由なく漫然と毎日飲む習慣はすでにアルコール中毒に片足を突っ込んでいる可能性があります。
肝硬変やがんになってしまったら、「減酒」ではなく「断酒」しなくてはなりません。
長くおいしくお酒を楽しむためにも、習慣的飲酒はやめて特別なときだけ飲む「機会飲酒」に切り替えてみませんか。